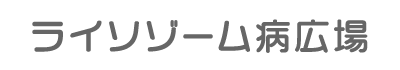「食べる喜び」をあきらめない
ライソゾーム病患者さんの食生活について医師が解説
生きるために欠かせない「食べる」という行為。
特に、闘病中の患者さんにとって、食事を摂ることは病気と闘うための生命エネルギーを得る貴重な機会であり、
非常に重要な意味を持つものになります。
今回は、患者さんと共に病気と闘う存在である医師の立場から見た「患者さんの食」についての見解を、
先天性疾患のスペシャリストである医療法人 医誠会国際総合病院 難病医療推進センターの酒井規夫(さかいのりお)先生と
成田綾(なりたあや)先生にインタビューいたしました。
本記事では、その内容について詳しくお伝えしていきます。
先天性疾患の専門医から見た「患者さんの食」について
酒井先生と成田先生は、先天性疾患の専門医として第一線で活躍しており、中でも特に先天性代謝異常症の診療に尽力されています。
お二人の先生は、「難病医療推進センター」を拠点に、先天性代謝異常症の一種である「ライソゾーム病」の診療を中心に、様々な先天性疾患の患者さんの治療環境の整備などにも力を入れています。
ライソゾーム病とは、生まれつきライソゾーム内の酵素の欠損もしくは機能低下があることで、生命維持の要となる代謝が正常に行われず、様々な症状を引き起こすという疾患です。
症状の現れ方や重度については、個々の患者さんによって異なりますが、幼少期から患者さんご本人とご家族、医師の連携によって長期的な治療を要します。
そのため「食の在り方」について、診療を通して医師の立場から考える機会が多くなっていると言います。


ライソゾーム病の患者さんは、細胞内の老廃物を処理する「ライソゾーム」という細胞内小器官内で分泌される分解酵素の働きが遺伝的に欠損しているため、大量の脂質やムコ多糖がライソゾーム内に蓄積していき、それが症状の発生に繋がります。
しかし、蓄積している脂質やムコ多糖は代謝によって発生している物質であり、食事として外部から何らかの食材を摂ったために発生したものではないため、ライソゾーム病の患者さんにおいては特別な食事制限というものは基本的に無いとのこと。
但し、先天代謝異常症の中では欠損している酵素の種類や症状の出方によって、例えば特定のアミノ酸をなるべく摂らないようにする等といった食事の指導が重要で、患者さんごとに実施しているそうです。
「食べる」という行為の重要性

酒井先生によると「ライソゾーム病の場合、7割程度の患者さんに神経症状があり、身体の機能が時間の経過とともに退行していくため、今まで食事を摂れていた子も、食べるということが出来なくなってしまう。食べようと思っても、むせたり、のどに詰まったり、誤飲したりします。
そうなると、次は鼻注(鼻からチューブを挿入して栄養を摂取する方法)にするか、胃ろう(胃に直接栄養を注入する方法)にするのか等といったように、食べ方自体を変える必要が出てくる。」とのこと。
それに加え「身体の機能の退行によって寝たきりになっていくと、代謝が下がり、普通の子と同じように食べると身体が太ってきてしまう。そうなると、患者さん本人も介護をしている家族も大変なので、運動レベルに応じたエネルギー摂取の管理について相談や指導を行う必要がある」といった事についても言及していました。
ライソゾーム病の症状の出方は患者さん毎に異なり、身体の機能の退行度合いも様々。
だからこそ、患者さん一人一人に合った食事の形状や食べ方を考えていくことに重きを置き、患者さんの「食べる」という行為を大切にしていきたいというのが、両医師の見解となっています。
「栄養食」による食事面のサポートと食事を楽しむ意義について
成田先生によると,最近は、患者さんの栄養摂取面をサポートする様々な種類の栄養食が国内で販売されてきているため、それぞれの患者さんの好みやこだわり等を考慮しながら、病院で出される食事と併用すること、在宅の際に活用するようアドバイスすることもあるそうです。
特に、ライソゾーム病の患者さんのように、神経症状によって身体の機能が退行し、噛んだり飲み込んだりするという動きが困難になっている場合においては、栄養食の利用によって食事を用意する側の負担が減ったり、患者さんに様々なフレーバーを楽しんで頂けるという大きなメリットを享受することができます。
但し、これらの栄養食の殆どは少量での販売に対応していないため、一度にまとまった数量の注文が必要になり、複数の商品を少しずつ気軽に試すことができないという点や、日本国内で栄養食に対する金銭的な補助が無く、経済的に余裕のある家庭でなければ継続的に購入していくのは難しいといった問題があるとの事でした。

そのため、これらの問題が解決され、もっと患者さんやご家族がバラエティ豊かな栄養食を気軽に試せる、少しずつ購入して楽しめる機会が増えれば望ましいと成田先生は述べられています。
また、介助による食べるという行為自体が「家族との大切なつながりでもある」と酒井先生は述べており、一緒に食事を行うこと、介護の場合は食事を食べさせることによって、相互のつながりを感じる貴重な機会であることについても言及。
医師目線から見て、患者さんの食事は「生きるために欠かせない行為」に留まらず、「家族とコミュニケーションを取る場」としても非常に大切なものであるというのが両医師に共通する意見となっています。
今回インタビューを行った酒井先生・成田先生のように、第一線で働いている医療従事者にとって「患者さんの食を取り巻く環境」の改善は、取り組むべき重要な課題の一つ。
今後のご活躍により、良い方向へと向かっていくことを期待し、本記事を締めくくりたいと思います。
〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町4−14
医療法人医誠会 医誠会国際総合病院
難病医療推進センター
難病医療推進センター 副センター長
酒井 規夫 先生
インタビュー・作成
一般財団法人 日本患者支援財団 運営事務局
〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町4−14
医療法人医誠会 医誠会国際総合病院
難病医療推進センター
小児科 部長
成田 綾 先生