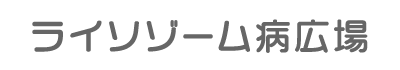「伝えたい」がきっと伝わる
ライソゾーム病患者さんのコミュニケーションについて医師からアドバイス
患者さんが自身の病気と向き合い、不安や悩みを解消していくうえで重要な役割を果たしているのが、
人との接触による「治療中のコミュニケーション」です。
特に、ライソゾーム病など幼少の頃から長期的な治療を必要とする先天性疾患を抱えている患者さんにとって、
専門医や自分と同じ病気と闘っている仲間と繋がることは非常に有益で、精神的な支柱としても機能する大切なものとなっています。
今回の記事では、専門医の目線から見た「患者さんのコミュニケーション」について、
医療法人 医誠会国際総合病院 難病医療推進センターの酒井規夫(さかいのりお)先生と成田綾(なりたあや)先生のお二人にお話しいただきました。
患者さんを支える「患者会」の存在
治療中の患者さんのコミュニケーションについて考える際、他の患者さんやご家族、そして専門医と繋がりを持てる場にアクセスできることが非常に重要であり、その役割を担っているのが「患者会」という存在です。
患者会では、勉強会などの開催により、専門医による講演や質問事項の受付などがあり、普段なかなか聞くことの出来ない話を直接聞き、情報を仕入れることができる貴重な機会を作っています。
酒井先生や成田先生が専門にしているライソゾーム病に関しては、現在新しい治療方法の開発が進んできているため、それぞれの患者会でも最新の治療法や基礎研究の内容を聞きたいと度々リクエストがあるとの事です。
その他、身体の機能の退行による嚥下障害に対する支持療法に関することや、安全に食事を摂る方法や栄養食について等、日常生活のケアに関する話題に興味を持っている方も多く、それについての話を聞きたいと言われる機会もよくあるそうです。


また、患者さん同士やご家族同士などで交流を持てるのも大きなメリットとなっており、治療中の悩みの解決方法をはじめ、利用してみて良かった食品や器具の話題などの情報を積極的に交換し、横のつながりを広げている方も多いと言います。
ただ、中には大勢の人の中で質問しにくいという方や、現地に足を運ぶのが難しい方、
実際に同じ病気を抱える先輩に会うことで「子どもが将来このような状態になるのかと知ってしまうのが怖い」という方も中にはいらっしゃるため、最近はネットで質問を受け付ける機会を設けたり、大勢ではなく一対一で話せるピアカウンセリングの機会を設けたり、場合によってはオンラインミーティングを実施する等といった工夫を行い、様々な事情の方が参加しやすい体制を整えているそうです。
社会生活におけるコミュニケーションの課題

このように、患者会で専門医や同病の患者さん同士、その家族同士で繋がり、コミュニケーションを取る部分に関しては様々な機会が増えてきている反面、一旦病院の外に出て一般の社会生活を営むとなると、その状況は全く異なるとの事。
病気のことについて知識のない人が大多数の環境に本人,家族が置かれることで、患者さん自身やご家族がコミュニケーションに苦労する場面は、まだまだ多いそうです。
社会生活と治療を上手く融合するためには、患者さんの通っている学校にいる担任の職員先生の方や、職場の上司・同僚の方に病気のことについて知ってもらうことが大切であるというのが両医師の見解で、例えば幼稚園や小中学校の入学前などの節目に保護者と先生や職員がコミュニケーションを取り、どんな時にどの程度の配慮が必要かを伝え、確認しておくことが非常に重要であると言います。
「病気についてお伝えする際、分かりやすいよう疾患のパンフレットや治療薬の実物を見ていただき、それらが無い場合は主治医が疾患に関する資料を作って、学校などに伝える際のサポートを行うこともある」と成田先生は話しています。
また、患者さん本人も、学校の友人や職場の同僚等にどう伝えていくかといった点も課題になっており、それを伝えても構わないと考えている患者さんもいれば、絶対に知られたくないと思っている患者さんもいて、そこは本人の価値観や置かれている環境によるものもあるので、どの範囲まで伝えていこうかと患者さんと主治医でコミュニケーションを取りながら決めていくこともあるそうです。
そういったコミュニケーションを積み重ねている甲斐もあり、病気を抱える子どもに対し、教育現場である学校ではかなり配慮して頂けることが多くようになってきたとの事。
しかし、一般の職場においては疾患に関する理解がそれ程進んでおらず、病気を抱えている人を配慮しながら仕事をしていくという事に関し、医師の立場から見てもまだまだ抵抗があるといった空気感が伝わってくるようです。
病気に関する認知と患者さんに対する偏見の解決へ
酒井先生はこう話します。
「職場という環境は、疾患に関する無知や拒否感というものがすごく伝わってくることが多くて、疾患を抱える人を受け入れることに対し、困りますという感じが見て取れる。
そういう苦しさや困難を抱えている人を適材適所で働かせてもらえるのが望ましいと思っても、それを実現するのはなかなか難しい。」
それに加え、疾患を持っていることを職場に知られたくないために、
健康保険を利用診察する診療を気にして通院をしなくなる、わざわざ遠方の病院に通院するケースもあり、職場や社会全体からの「人の目」を気にしている患者さんも多いと言います。

このように、社会全体における難病や遺伝的な疾患に関する知識の無さや偏見により、病気を抱えている患者さんが社会生活を営むうえで周囲と馴染めなかったり、隠れるように暮らしていたり、コミュニケーションに困るという場面がしばしば存在し、それがなかなか無くならないという問題点があるとの事。
この問題が少しずつでも解決に向かうよう、医療従事者だけではなく教育の現場や仕事の場での認識が変わっていって欲しいというのが両医師の見解となっています。
今後、日本国内で難病に対する理解が進み、病院の外で患者さんが社会生活を営むうえで円滑なコミュニケーションを取れる環境になっていくことを願い、今回のインタビュー記事を締めくくりたいと思います。
〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町4−14
医療法人医誠会 医誠会国際総合病院
難病医療推進センター
難病医療推進センター 副センター長
酒井 規夫 先生
インタビュー・作成
一般財団法人 日本患者支援財団 運営事務局
〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町4−14
医療法人医誠会 医誠会国際総合病院
難病医療推進センター
小児科 部長
成田 綾 先生